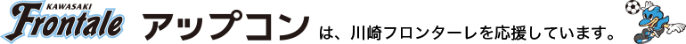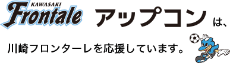地盤沈下はなぜ発生する?原因と対処方法について

地盤沈下は、建物や土地利用に大きな影響を及ぼす現象のひとつです。沈下が進行すると、建物(床)の傾きや床の段差、クラック(ひび割れ)などが発生し、事業や生活に支障をきたすだけでなく、安全性にも深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
この記事では、地盤沈下が発生する主な原因と、それに対処するための方法について詳しく解説します。
目次
地盤沈下とは

地盤沈下とは、自然災害や人為的要因によって地盤面が沈下する現象を指します。この現象は、建築物や工作物の基礎に深刻な影響を与え、床の傾きや基礎の損傷を引き起こすことがあるのです。
地盤沈下が発生すると、建築物の基礎が時間の経過とともに不均等に沈むことがあります。その結果、床の傾きや基礎梁への過剰な負荷が発生し、建物全体の構造が不安定になる可能性が高まります。
こうした問題を放置すると、大規模な修繕が必要になるだけでなく、安全性の面でも大きなリスクを伴います。そのため、地盤沈下が確認された場合は、迅速かつ適切な対応が求められるのです。
地盤沈下の原因
地盤沈下は、さまざまな要因によって引き起こされます。以下では、主な地盤沈下の原因を詳しく説明します。
地下水の汲み上げ
地下水を過剰に汲み上げることによって、粘土層が収縮するため、地面全体が下がり地盤沈下します。
地下水の利用が多い地域では、この原因による地盤沈下が深刻な問題となることが多い傾向にあります。
工事による影響
地下トンネルや地下鉄の建設工事、新築マンション工事など、地下構造物を設置する際に発生する掘削工事が地盤沈下の原因となる場合があります。
掘削に伴い地盤強度が弱くなり、地盤の安定性が損なわれ、地盤沈下することがあります。また、周辺地域の構造物にも影響を及ぼすリスクがあります。
圧密による沈下
軟弱な粘性土層が盛土や建造物の荷重を受けて、土と土の間の水が徐々に排水されて体積が減少する現象を圧密沈下と呼びます。
特に、地盤が柔らかい場合や水分を多く含む場合、圧密沈下が発生しやすくなります。
液状化現象
地震によって引き起こされる液状化現象も地盤沈下の主な原因の一つです。液状化とは、地震の揺れによって地盤が一時的に液体のような性質を持つ現象です。
この結果、建物の基礎が不均等に沈み込んだり、地表が陥没したりすることがあります。この液状化現象は、特に砂質土壌の多い地域で顕著に見られます。
地盤沈下は、これらの原因が単独の場合もあれば、複数の要因が重なる場合もあります。それぞれの原因に応じた対策を講じることで、地盤沈下による被害を最小限に抑えることが可能です。
地盤沈下の影響

地盤沈下は、建物や周囲の環境にさまざまな影響を及ぼします。以下で、特に顕著な影響について解説します。
建物への影響
地盤沈下は、特に土間床構造を持つ建物に深刻な影響を及ぼします。土間床構造では、土間コンクリートが地盤に直接支えられることを前提に設計されていますが、地盤沈下すると、それに追随して床も沈下します。
沈下量が大きくなると、土間コンクリートが地盤から完全に浮き上がり、宙に浮いた状態になることがあります。また、地中梁に筋結されている部分は沈下しにくいため、床全体に傾斜が生じる場合も。このような状態を放置すると、以下のような問題が発生します。
- 床の沈下や傾斜:建物の機能性が損なわれ、使用や運営に支障をきたします。
- 床のたわみや段差:歩行の安全性が低下し、事故につながる恐れがあります。
- クラック(ひび割れ)の発生:コンクリートが地盤に支持されずず、クラック(ひび割れ)が生じます。状況によっては鉄筋が破断し、床が崩落するリスクもあります。
- 空隙・空洞の発生:床下の地盤が沈下することで空洞が生じ、建物の安定性が低下します。
これらの問題は、建物の耐久性を大きく損なうだけでなく、安全性を著しく低下させる可能性があります。そのため、地盤沈下が確認された場合は、早急に適切な修正工事を行う必要があります。
インフラへの影響
地盤沈下は、建物だけでなく道路や橋梁、水道管、ガス管などのインフラにも深刻な影響を及ぼします。道路が陥没することで交通が遮断されるだけでなく、上下水道管が破損して漏水が発生。
これらは地域全体に大きな被害をもたらし、復旧には多大なコストと時間が必要となります。
環境への影響
地盤沈下が広範囲にわたる場合、周囲の生態系にも影響を与えることがあります。たとえば、地下水の流れが変わることで湿地や河川が乾燥し、生態系が崩れる可能性があるのです。
また、海岸近くで地盤沈下が発生した場合、海水が侵入して土地が塩害を受けるリスクも考えられます。
地盤沈下による傾いた床を修正する工法
地盤沈下がすでに発生している場合、適切な沈下修正工法を用いて、建物の安全性を回復させることが重要です。以下に、代表的な4つの修正工法を示します。
コンクリート打替え工法
沈下した部分の土間コンクリートを完全に撤去し、地盤を再度締め固めた上で新たなコンクリートを打設する工法です。この工法では地盤自体を強化し、修復後の地盤沈下リスクを低減できます。
メリットとしては、地盤がしっかり補強されるため、仕上がりが美しく長期的な耐久性が期待できる点があげられます。
一方で、デメリットとしては、工期が長く、施工中に建物の一部機能を停止する必要があることや、騒音や振動が発生する点があります。
ウレタン注入工法
土間コンクリートの下に特殊なウレタン樹脂を注入し、発泡圧力で沈下部分を持ち上げる工法です。この工法は、施工が迅速であり、建物を使用しながら修正が可能となっています。
床を壊す必要がないため、操業を中断せずに施工できるのが特長です。また、発泡ウレタンは軽量であり、再沈下リスクも低減されるメリットがあります。
ただし、費用が比較的高くなる傾向にあり、さらに、床下の埋設物など建物の構造に配慮しなければなりません。
コンクリート増し打ち工法
既存の土間コンクリートの上に新たなコンクリートを重ねて厚みを増し、床面を平らにする工法です。この工法は比較的安価で、短期間で施工が完了するのが特徴です。
しかし、デメリットとして、沈下した地盤がそのまま残るため、将来的な再沈下のリスクが高まる可能性があります。また、床が重くなることで、さらに地盤に負荷がかかる場合もあるので注意が必要です。
表面処理工法
沈下した床の表面を薄い層で修正する工法です。樹脂モルタルやレベラー材を用いて床面を平滑に整えます。この工法は、施工が簡易であり、費用が比較的安価で済むのがメリットです。
ただし、30mm程度までの薄い層しか対応できないため、大規模な沈下や空洞には適していません。また、既存のクラック(ひび割れ)部分に再び亀裂が生じる可能性もあります。
アップコン工法の特長
アップコン工法は、沈下・段差・傾き・空隙・空洞が発生したコンクリート床を修正するための技術です。
この工法では、床下の地盤にウレタン樹脂を注入し、その発泡圧力によって地盤を圧密強化しつつ、地耐力を向上させます。これにより、床を下から押し上げて元の高さに戻すことができます。
ウレタン樹脂は、注入された位置から半径約1mの範囲に効果を発揮します。そのため、注入間隔を広げすぎると、床下に空隙や空洞が残り、再沈下のリスクが高まる恐れも。また、適切な箇所に樹脂を注入しないと、床全体に負担がかかり、ひび割れが発生する恐れがあります。
そこで、アップコン工法では原則として1m間隔で樹脂を注入し、床下全体を隙間なく充填します。この方法により、再沈下の可能性を大幅に低減します。
また、施工時には注入を行う作業者と測量を担当する作業者を分け、ミリ単位でレベル管理を徹底しています。これにより、床に負荷をかけることなく正確な修正が可能になります。

さらに、この工法では直径16mm程度の小さな穴を床に開けるだけで作業を行うため、既存のコンクリート床を取り壊す必要がありません。
そのため、工場や倉庫、店舗などでは機械や荷物を移動させずに施工が可能です。最短1日で作業が完了し、ウレタンの最終強度も約60分で発現するため、業務や営業を止めずに迅速な施工が実現します。
詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問等については「アップコン工法とは」をご覧ください。
地盤沈下の対策は「アップコン工法」で
今回は、地盤沈下の原因とその対策方法について解説しました。
弊社が独自に行うアップコン工法の特長は、沈下・段差・傾き・空隙・空洞が生じたコンクリート床を壊さずに修正できることです。床を壊さずに施工を行うため、荷物・機械等の撤去作業や大型プラントの設置なども不要となり、操業を止めずに施工が可能です。
また他の特長として、
- 施工の体制がコンパクトなため速やかに原状回復が可能
- 従来工法に比べ再沈下のリスクを低減(ウレタン樹脂は、コンクリートやモルタルと比較し軽量なため)
- 既設コンクリート床を壊さずに施工可能なため、コンクリートを解体する際に発生する産業廃棄物のコストや、大きな騒音が発生しない
などがあります。
また、ウレタン樹脂の影響範囲は約1~1.5mのため、アップコン工法は1m間隔でウレタン樹脂を注入することで、
- 空隙・空洞を100%充填
- ミリ単位でのレベル管理で沈下を修正
- 床のひび割れの発生を極力抑え床に負担をかけずに沈下を修正
を可能にしています。
詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問などについては「アップコン工法とは」をご覧ください。
“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・店舗・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラを長寿命化させることで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。
また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。
「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。


 トップメッセージ
トップメッセージ アップコンについて
アップコンについて 企業情報
企業情報 資格保有状況・
資格保有状況・ コーポレート
コーポレート ISOへの取り組み
ISOへの取り組み 環境への取り組み
環境への取り組み 健康経営
健康経営 ブランド・
ブランド・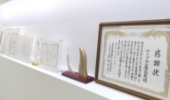 特許・受賞一覧
特許・受賞一覧 メディア紹介
メディア紹介 工場
工場
 倉庫
倉庫 道路
道路 商業施設・店舗
商業施設・店舗 港湾
港湾 ベタ基礎住宅
ベタ基礎住宅