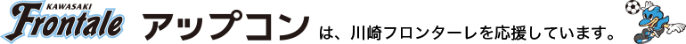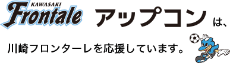第532号(2025/9/19発行)空洞6か所発見?
※この記事は沈下修正の専門家アップコンの社長メルマガ〔ニッポン上げろ!〕のバックナンバーです。
→【メールマガジンの新規登録はこちら】
こんにちは!
コンクリートを上げるからアップコンの松藤です。
国土交通省は17日(水)、
下水道管路の全国特別重点調査(優先実施箇所)の結果(8月時点)
を発表しました。
これは今年1月に埼玉県八潮市で起きた道路の陥没を受けて
全国の自治体に要請した下水道管路の特別調査の結果です。
さて、この結果をどう見れば(判断すれば)よいでしょうか。
8月8日までに結果が出た管路621キロの内訳は、
・緊急度Ⅰマンホール間延長 約104km
・緊急度Ⅱマンホール間延長 約385km
・異状なしまたは軽度の異状 約132km
でした。
さらに、
・緊急度Ⅰ 要対策延長※1 約72km
・緊急度Ⅱ 要対策延長※2 約225km
となりました。
※1原則1年以内の速やかな対策が必要と見込まれる推計延長
※2応急措置を実施した上で5年以内の対策が必要と見込まれる推計延長
※出典:国土交通省(報道・広報): 【別紙1】全国特別重点調査(優先実施箇所)の結果の概要
それではなぜ、下水道管を調査するのでしょうか?
2022年は全国で1万件以上もの道路陥没が発生しています。
道路陥没発生の要因として最も多いのは
道路排水施設や道路側溝などの道路施設が要因の陥没が
直轄国道では46%
都道府県道では68%
市町村道では51%
と、約5割を占めています。
次に多いのが上下水道などの道路占用物件が要因の陥没が
直轄国道では17%
都道府県道では8%
市町村道では18%
と、約2割を占めています。
ところが人口の密集する都市部の数値を抜粋してみると
道路施設が要因の陥没と道路占用物件が要因の陥没の割合は
それぞれ
直轄国道では26%と37%
都道府県道では27%と37%
市町村道では13%と57%
というように
道路占用物件が要因の陥没の割合の方が高くなっているのが分かります。
※出典:国土交通省「道路の陥没発生件数とその要因(令和4年度)」
人口密集地での下水管調査をすることによって、
人的被害を最小化するという狙いでしょうか。
それでは今回の下水道管調査によって、空洞は見つかったのでしょうか?
緊急度ⅠまたはⅡのマンホール間延長のうち約285kmの空洞調査
を実施しました。
調査方法は路面や管路内からの空洞調査、簡易な貫入試験などです。
その結果、空洞が確認された箇所は6か所。
北海道北見市1か所、新潟市2か所、熊本県玉名市3か所です。
うち4か所で対策済み、残り2か所は陥没の可能性は低いが 早急に対策実施予定、
ということです。
「6か所見つかってよかったな。」
というのと、
「たった、6か所しかなかったの?」
というのが私の感想です。
全国特別重点調査の「優先実施箇所」で
さらに緊急度ⅠまたはⅡのマンホール間延長約285km
を調査した結果が、空洞6か所でした。
しかし、道路陥没は年間10,000件以上起こっています。
1日あたり平均約30件です。
日本の全管路延長は約49万kmあります。
「空洞が6か所見つかって、すでに4か所は対策済みです。
残りの2か所においても早急に対策を実施する予定です。」
というのはどのように受け止めたらよいのでしょうか。
数か月にわたる、全国の優先実施箇所で行われた調査で
見つかった空洞が6か所。
でも、毎日30件の道路陥没が起こっています。
今回の発表の前日16日(火)には
同じく、国土交通省から基準地価が発表されました。
全国的な上昇基調の中、埼玉県八潮市の現場周辺は前年から横ばいとなりました。
「大規模なインフラ事故が起きれば地価の下落につながる恐れがあり、
老朽化対策は急務だ。 」
と国交省の担当者の話がニュースになっていました。
空洞6か所発見も事実なら、
年間10,000件以上の道路陥没も事実です。
この結果をどう見れば(判断すれば)よいのでしょうか?
引き続き、調査結果を見守りながら、
アップコンは、今後もインフラの維持に貢献していきたいと思います。



 トップメッセージ
トップメッセージ アップコンについて
アップコンについて 企業情報
企業情報 資格保有状況・
資格保有状況・ コーポレート
コーポレート ISOへの取り組み
ISOへの取り組み 環境への取り組み
環境への取り組み 健康経営
健康経営 ブランド・
ブランド・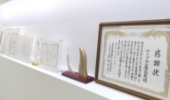 特許・受賞一覧
特許・受賞一覧 メディア紹介
メディア紹介 工場
工場
 倉庫
倉庫 道路
道路 商業施設・店舗
商業施設・店舗 港湾
港湾 ベタ基礎住宅
ベタ基礎住宅